剣道の構えにはいくつか種類がありますが、最も一般的なのは中段の構えでしょう。
しかし実際の試合では、上段の構えを使う選手もおり、対策が出来ていなければ驚くかもしれません。
それゆえ、自分が上段の構えを使わないとしても、剣道選手として上のレベルに行きたいなら、上段の構えについて知っておく必要があります。
そこで今回は、上段の構えのメリットやデメリット、必要な要素などに焦点を当てて解説します。
上段の構えに必要なもの
剣道における上段の構えは、別名「火の構え」と呼ばれ、完全攻撃特化型の構えです。
この構えを満足に扱うには、「絶対的な自信」、「何事にも動じない度胸」、「鍛え上げられた腕力」が必須です。
自信や度胸に関しては精神的な要因なので、場合によってはちょっとした切っ掛けで身に付くかもしれません。
ですが、腕力だけはそうはいきません。
左腕一本で竹刀を操れるほどの腕力が必要で、最低でも片手素振り300本程度は出来るようにならなければなりません。
これは言葉にするほど簡単ではありませんが、出来るようになれば打突に鋭さが生まれ、結果的に自信に繋がることもあるでしょう。
上段の構えのメリットとデメリット
上記では剣道の上段の構えを習得する為に求められる要素を解説しましたが、ここではそのメリットとデメリットを説明します。
これらを知ることで、上段の構えを学ぼうとする人も、対策したい人も糧に出来るはずです。
まずメリットですが、竹刀を常に頭上に掲げていることで、有効打突部位への距離が短くなり、素早い攻撃が可能だと言うことが挙げられます。
更に、両手打ちだけではなく片手打ちが出来るので、遠間から一気に攻められると言う利点もあります。
ただしこれ実行するには、上記でも述べた相当な腕力が必要だと言うことを覚えておきましょう。
また技術面以外では、相手に体を大きく見せて威圧感を与えることも出来ます。
それでは、デメリットは何でしょうか。
一つは、上段の構えは中段の構えと足さばきが逆になるので、慣れるまではろくに動くことすら出来ません。
これを克服するには、毎日徹底的に足さばきを練習する必要があります。
そして、メリットで挙げた片手打ちですが、片手打ちは両手打ちに比べてより一層完璧な打突を求められるので、一本を取るには相応に練習しなければなりません。
言うまでもなく、中段の構えとは軌道が全く違うので、感覚を矯正するだけでも大変でしょう。
あとは、少し考えてみればわかることですが、上段の構えはその性質上、面以外の守りががら空きです。
それゆえに、「打てるものなら打ってみろ」と言う自信と度胸が必須なのです。
以上が剣道における上段の構えに関する解説ですが、最後に知っておいて欲しいことがあります。
それは、中段の構えから上段の構えに転向すると言うことは、剣道を一から学び直すほどの覚悟が必要だと言うことです。
足さばきも竹刀の振り方も違うので、それまでの固定概念を捨て去らなければならないからです。
それでも上段の構えを習得する価値はあるので、強い決意を持って取り組むようにしましょう。
失敗しない剣道上達教材の選び方のご案内
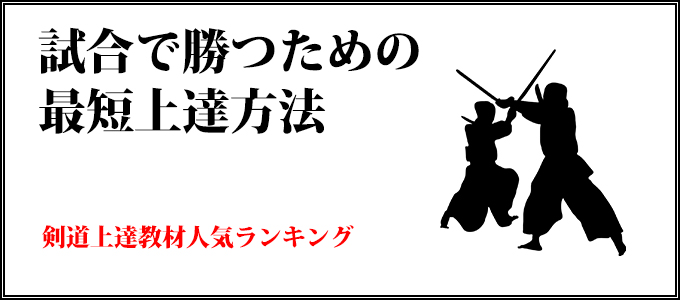
「強くなりたい」と心底願う少年から大人の方とまた毎日一生懸命稽古している剣士を勝たせたい思う監督や親御さんに絶対に後悔しないオススメできる剣道上達教材をランキング形式で紹介します。
自己流には限度がありいつまでたっても勝つことはできません。
正しい練習法を学ぶことで自己流で練習している人より早く上達できます。
⇒剣道上達人気(DVD)教材ランキング
さらに剣道のスキルを磨きたい方へ
剣道の成長は、継続的な練習と正しい知識が欠かせません。
より効果的に技術を向上させるための専門的な教材をお探しの方は、こちらの推薦教材をチェックしてみてください。
初心者から上級者まで、あなたのレベルに合わせた内容が揃っています。一歩先を行く剣道のスキルアップを目指しましょう!
→剣道優良教材ランキングの詳細はこちら
